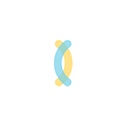
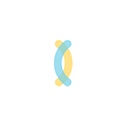

以前のブログで冷えの原因を書いていきましたが、今回は東洋医学から見る改善方法や治療について、書いていきたいと思います(^^♪
様々な原因によって「気」「血」「水」の動きが停滞して「冷え」という状態になっていくのですが、東洋医学の観点から治療を考えていくと次の臓腑が重要になってきます。
身体を動かしていくのに必要なエネルギー(栄養分)である「気」「血」をスムーズに運ぶ働きのある「肝」、身体全体の水分の代謝、また陽気の元である「腎」、食べ物からエネルギー(栄養分)を作り出す「脾」「胃」が深く関わっています。
「肝」は「血」の流れを調節してスムーズに運ぶ「疏泄」という働きがあります。この機能が弱まっていると栄養が行き渡らないのですが、これをよくすれば良いというだけではないのです。「血」が足りなければもちろん身体の隅々まで行き渡らないので、先に「血」を補わなければなりません。「肝」に「血」が満ちていれば「疏泄」の働きが自ずと回復していくのです。
「腎」は水分の代謝の働きがあります。「水」は陰陽の分類では陰で、「水」を動かすためには「気」が必要になってきます。また、「気」は陽の分類で、陽気が必要なのです。そして「腎」は「陽気の元」と呼ばれ、腎の陽気が足りないと水分の代謝がうまくいかなくなり、同時に身体の冷えも感じやすくなってしまいます。
「脾」「胃」は飲食物を消化・吸収して、全身に運搬する働きのある「運化」という働きがあり、他の臓腑は「脾」が作り出し、運んでくれる「気」「血」を受け取って動いています。だから「脾」の働きが弱ると全身に影響を及ぼしてしまうのです。胃腸の調子が弱っている時にも冷えに注意してくださいね。
患者さんに一人一人に原因は違うのもありますが、「気」「血」「津液」のいくつかに原因がある場合が多いようです。特に女性は生理の時期になると「気」は「血」と一緒に出ていってしまうので、いつもよりも冷えやすくなります。生理の時期などはなるべく身体が冷えない工夫をしましょう。
金魚庵の冷えに対する鍼灸治療としては、腎に属する「太溪」や脾に属する「三陰交」、胃に属する「足三里」を使うことが多いですね。鍼やお灸を組み合わせて、治療しております。また、生活の中で、入浴・運動・食生活などを工夫することも「冷え症」改善に大切です。合わせてアドバイスさせていただいてます!お気軽にお問い合わせください。
© 2015-2025 はりきゅうマッサージ治療院 金魚庵